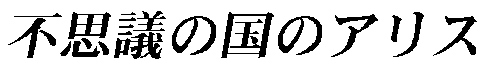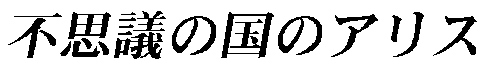テニスコートに戻ったつもりだったのに、似たような広場にいすが並んだ場所へ出た。奥には玉座。クイーンとキングが並んで座っている。
少し手前の両脇にテーブルがあって右側は空いていた。左側には猫を追っていたおじさんと、見たことのない叔父さんの二人が座っていた。
小さな柵のようなもので区切られた外側にたくさんの動物たちがいて、てんで勝手に話をしていた。
「これは何ですか?」
一番近くにいた大きなネズミみたいな動物に声をかけると、面倒くさそうにこっちを向いて答えてくれた。
「裁判だよ」
「じゃあ、女王と王様は裁判官なのね。あのおじさんたちが検察官かしら。向こうの席が被告と弁護士?どうして空っぽなのかしら。これはいったい何の裁判なの?」
「本当の女王」とやっと聞こえるほど小さな声で言ってから「…がパーティに来なかったんだよ。その裁判さ」
「どうしてパーティに来なかったの?」
「女王が呼ばなかったからさ」
「呼ばなければ来れる訳ないわ。何で呼ばなかったのかしら」
「しいっ」と周りの動物たちが言う。
集まっている動物たちは自分は関係ないとでも言いたげにアリスと目を合わせなかった。
今度はアリスも小さな声で聞いた。
「何で本当の女王を呼ばなかったの?」
「ハートのクイーンが呼ばなかったのさ。本当の女王の方が…うつくし…やさし…からね」
ところどころ声が聞こえないくらい小さかった。
「でも、呼ばなければ来ないのは当たり前でしょう?どうして裁判になったの?」
「パーティなのに来なかったからだよ」
またここでもドードーメグリになってしまった。
「本当の女王は裁判なのにどうしていないの?わたし、本当の女王に会いたいわ」
「呼ばなかったのさ。ハートのクイーンは2番目になるのが嫌いだからさ」
「変なの」
つい、声を大きくなって裁判所に響き渡った。
ハートの女王はちらりとこちらを見、口を開く。
「お裁判所ではお静かにするものですよ」
そしてついに本当の女王は来なかった。弁護士もいないままケッセキ裁判が始まった。
「なぜお出でにならなかったのですか?」とハートの女王が問う。
「女王陛下がお呼びにならなかったからです」と検察官役の頭のてっぺんが禿げたおじさんが答えた。
「わたくし、そんなこといいません」
「は、はいっ。そのようなことをおっしゃるはずはございません」
おじさんの隣にいるメッシュの髪のおじさんが目をぐるぐるを回しながらいきなり話しだした。
「あちらとは会う機会があまりなく…娘は爽やかな学生生活で…わたし…もしくは…意見を聞いていただいて…赤信号が…紙細工…えっと…なんといいましょうか、ねえ?」
急に禿げたおじさんを見て、すぐ知らん顔で目をぐるぐると回す。
「太極拳などをするのがよいと思います」いつの間にか帽子屋が来ていた。相変わらず表情を変えずまっすぐ前を見て座っていた。
「リコンだ」誰かが叫ぶ。
「見捨てられることは決してないと思います」また帽子屋。
「新型だ」
「ガイドラインにあわない」
「やつあたりだ」
みんなが口々に騒ぎだした。誰かに言うというのではなく、勝手に自分の言いたいことを言っている。
「失礼よっ」とアリスは我慢が出来なくなって大きな声で言った。「いない人の裁判をするのも、色々言うのも失礼なことだわ」
「だれか、いらしゃる?」と女王。「その子どものお首をおはねなさい」
女王の言葉を聞くとみんな一斉にアリスに飛びかかる。
両手で顔を隠し、目を閉じて走った。
とにかく、全力で、どこまでも走った。
周りが静かになったので目を開くと、ここはよく知っているところ。お家の前に立っていた。
気がつくと猫たちが足許にいてニャーと鳴いていた。
「ママと子どもたちかしら?」
しゃがみこんで猫をなでていると扉が開いて中から優しい声。
「お帰りなさい」
大好きなママが迎えてくれた。ママは猫たちを見て目を細め、ちゃんと全部わかっているわ、というように頷いた。
「まず、この子たちにミルクをあげましょうね」
大きく頷きながらアリスは、今日は変なことばかりだったけどもう大丈夫だって思った。
だってママがいつもと同じように笑っているんだもの。
※9…女王は少々敬語がおかしいようです。
「ご尊敬申し上げる」とか「お点をつけるなら」とか言ったりします。
|